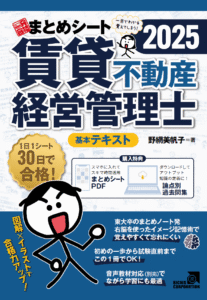今日は、平成30年度 第21問について解説します。
未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。
② 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。
③ 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。
④ 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。
解説
少額訴訟制度に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。
×不適切です。
少額訴訟とは、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、原則として1回の期日で審理を終え、即日判決を言い渡す民事訴訟手続です。
同一の原告(訴えている側)が少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において1年に10回までと制限されています。
つまり、債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、年10回を超えて少額訴訟を選択することはできません。(債務者が異なれば選択することができるという制度ではありません)。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。
×不適切です。
少額訴訟においては、事件の内容や証人の都合などに応じて、臨機応変に立証しやすくするための特則が設けられていますが、証人尋問手続き自体が取られないというわけではありません。
つまり、少額訴訟において証人尋問が必要な場合、事件の内容や証人の都合などに応じて、臨機応変に立証しやすくするための特則が設けられています。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。
〇適切です。
少額訴訟においては、必要に応じて、判決言渡しの日から3年を超えない範囲で、判決による支払いの猶予・分割払いを定めることが認められています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。
×不適切です。
原告が少額訴訟による審理を希望する場合には、訴えの提起の際に少額訴訟による裁判を希望する申出(申述)をする必要があります。
これに対して被告が少額訴訟によることに意義を唱えなければ、少額訴訟によるものとなります。
つまり、裁判所は、原告が少額訴訟を希望する旨の申述を行い、被告の異議がなければ少額訴訟による審理を行うことになります。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。